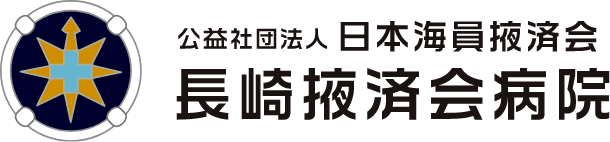病院概要
メニュー
病院概要
| 病院名 | 長崎掖済会病院 |
| 所在地 | 〒850-0034 長崎市樺島町5番16号 |
| 電話番号 | 095-824-0610 |
| FAX番号 | 095-822-9985 |
| 代表者 | 院長 末広 昌嗣 |
| 設立年月日 | 明治35年11月 |
| 病床数 | 124床(一般病床70床 地域包括ケア病床54床) |
| 従業員数 | 250名 |
| 診療科目 | 内科、消化器内科、心臓内科、呼吸器内科、気管食道内科、糖尿病内科、脂質代謝内科、感染症内科、老年内科、内視鏡内科、腎臓内科、外科、消化器外科、肛門外科、腫瘍外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、性感染症泌尿器科、放射線科、麻酔科 |
| 救急指定 | 救急告示病院 第2次救急輪番病院 |
| 認定施設 | (社)日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 (社)日本皮膚科学会認定専門医研修施設 (社)日本整形外科学会認定専門医研修施設 (社)日本外科学会外科専門医制度関連施設 臨床研修協力施設 |
| 指定医療機関 | 保健医療機関、労働者災害保険指定医療機関、結核予防法指定医療機関、社会福祉事業法指定医療機関、生活保護法指定医療機関、原子爆弾被爆者医療指定医療機関、出入国管理令の規定に基づく指定医療機関 |
| 新興感染症の発生時等の 確保病床数 |
3床 |
理 念
私たちは「掖済」の心で皆様と接します。
「掖済」とは、病む人の腋(わき)に手を添えて救い導くこと
基本方針
- 質の高い医療と患者の権利、人格を尊重する医療を目指します。
- 納得のゆく説明をいたします。
- 心休まる、安心できる看護を行います。
- 温かく、明るく、誠意をもって皆様と接します。
- 職員同士、助け合い、協力しあいます。
沿 革
| 明治13年 8月 | 日本海員掖済会創立 |
| 明治31年 10月 | 社団法人として登録 (民法による社団法人登録第1号) |
| 明治35年 11月 | 長崎海員病院開設(病床数 30床) |
| 昭和13年 3月 | 国内船及び外国船の無線電信による医療相談機関として逓信省より指定される |
| 昭和20年 8月 | 原爆のため長崎病院半壊、職員若干名負傷するも直に救援活動を行う |
| 昭和21年 3月 | 病床数12床で再開する |
| 昭和23年 12月 | 年末無料診療を開始(以後毎年実施) |
| 昭和24年 4月 | 病棟を増築して病床21床となる |
| 昭和26年 6月 | 労働者災害保険法及び身体障害者福祉法規定に基づく医療機関に指定される |
| 昭和26年 10月 | 結核予防法の規定に基づく医療機関に指定される |
| 昭和27年 5月 | 社会福祉事業法の規定に基づく医療機関に指定される 生活保護法の規定に基づく医療機関に指定される |
| 昭和29年 4月 | 4床増床して25床になる |
| 昭和35年 12月 | 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の規定に基づく医療機関に指定される |
| 昭和39年 7月 | 鉄筋コンクリート3階建の病院を建築、病床63床となる 標榜科目:内科、小児科、外科、皮膚泌尿器科、性病科、放射線科 |
| 昭和39年 10月 | 救急病院の指定を受ける |
| 昭和42年 9月 | 出入国管理令の規定に基づく医療機関に指定される |
| 昭和49年 6月 | 病棟の増築、旧病棟改造改装を行い、病床数100床となる |
| 昭和60年 8月 | 整形外科開設 |
| 昭和61年 7月 | 第二次救急輪番指定となる |
| 平成元年 4月 | 泌尿器科、小児科開設 |
| 平成2年 2月 | 新病棟の増築及び病棟改修工事竣工、病床数160床となる 標榜科目:内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、 整形外科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、理学療法科、放射線科 |
| 平成5年 6月 | 健康保険法の規定による適温給食加算取得 |
| 平成5年 9月 | 重症者収容部屋使用加算承認 |
| 平成6年 8月 | 小児科閉鎖 |
| 平成7年 4月 | 山下巖院長就任 |
| 平成10年 4月 | 健康保険法の規定によるペースメーカー移植術の施設基準に係る届出 |
| 平成11年 1月 | 健康保険法の規定による院内感染予防加算承認 |
| 平成13年 1月 | 病院勤務体制 完全週5日制とする |
| 平成16年 12月 | 健康増進法の規定により病院敷地内全面禁煙となる |
| 平成17年 4月 | 松尾 罣院長就任 |
| 平成19年 9月 | オーダリングシステム導入 |
| 平成20年 7月 | DPC準備病院となる |
| 平成20年 12月 | 亜急性期病床15床を届け出 それに伴い総病床数が一般病床143床、 亜急性期病床15床、合計158床に変更 |
| 平成24年 11月 | 電子カルテシステム導入 |
| 平成26年 7月 | 病院耐震化及び増築棟工事完了 MRI撮影装置導入する |
| 平成28年 12月 | 地域包括ケア病床を43床へ拡大。一般病床を99床とする |
| 平成29年 4月 | 大園惠幸院長就任 |
| 令和2年 4月 | 公益社団法人へ移行 |
| 令和3年 3月 | 地域包括ケア病床を54床へ拡大。一般病床を88床とする |
| 令和3年 4月 | 末広 昌嗣院長就任 |
| 令和5年 11月 | 病床数を削減 一般病床数70床、地域包括ケア病床54床、合計124床に変更 |
厚生労働大臣が定める掲示事項
| 入院基本料に関する事項 | 3階病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師・准看護師)と4人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 【2交代制】 8:30 〜 16:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、7人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、10人以内です。 16:30 〜 8:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、10人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、19人以内です。 4階病棟では、1日に14人以上の看護職員(看護師・准看護師)と7人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 【2交代制】 8:30 〜 16:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、7人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、10人以内です。 16:30 〜 8:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、17人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、49人以内です。 5階病棟では、1日に12人以上の看護職員(看護師・准看護師)と7人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 【2交代制】 8:30 〜 16:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、5人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、6人以内です。 16:30 〜 8:30まで ・看護職員1人当たりの受け持ち数は、10人以内です。 ・看護補助者1人当たりの受け持ち数は、30人以内です。 |
| DPC/PDPS算定病院に関する事項 | 当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC対象病院」となっ ております。 ※ 医療機関別係数 1.2347 (基礎係数 1.0063 + 機能評価係数Ⅰ 0.1558 + 機能評価係数Ⅱ 0.0674 + 救急補正係数 0.0052) (令和7年6月1日診療分から適用) |
| 九州厚生局長への届出事項 | 【基本診療料の施設基準に係る届出】 ・急性期一般入院料4 ・救急医療管理加算 ・診療録管理体制加算2 ・医師事務作業補助体制加算2(30対1補助体制加算) ・急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上) ・夜間50対1急性期看護補助体制加算 ・重症者等療養環境特別加算 ・医療安全対策加算1 ・感染症対策向上加算2 ・連携強化加算 ・患者サポート体制充実加算 ・後発医薬品使用体制加算3 ・データ提出加算2 ・入退院支援加算1 ・入院時支援加算 ・認知症ケア加算3 ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 ・地域包括ケア病棟入院料2 ・看護職員配置加算 ・看護補助体制充実加算3 ・入院時食事療養(Ⅰ) 【特掲診療料の施設基準に係る届出】 ・心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 ・夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 ・外来腫瘍化学療法診療料2 ・がん治療連携指導料 ・薬剤管理指導料 ・在宅療養支援病院3 ・検体検査管理加算(Ⅱ) ・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト ・画像診断管理加算2 ・CT撮影及びMRI撮影 ・冠動脈CT撮影加算 ・外来化学療法加算2 ・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)(初期加算及び急性期リハビリテーション加算) ・運動器リハビリテーション(Ⅰ)(初期加算及び急性期リハビリテーション加算) ・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)(初期加算及び急性期リハビリテーション加算) ・椎間板内酵素注入療法 ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ・医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 ・輸血管理料Ⅱ ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ・保険医療機関の連携による病理診断 ・看護職員処遇改善評価料47 ・外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ ・入院ベースアップ評価料48 ・酸素の購入単価 【入院時食事療養】 当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を 適時、適温で提供しています。 |
| 明細書の発行状況に関する事項 | 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成24年4月1日より領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただきご家族の方が代理で会計を行う場合その代理人に対しての発行も含めまして、明細書発行を希望されない方は、「会計窓口」にてその旨お申し出ください。 |
| 医療情報取得加算について | 当院では、医療情報取得加算を算定しています。 この加算は「オンライン資格確認を導入している医療機関の外来において、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して、質の高い診療を実施する体制を評価するもの」として位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。 ①オンライン資格確認を行う。 ②受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。 マイナ保険証を利用し、正確な情報を取得・活用することにより、より質の高い医療の提供が可能となります。マイナ保険証ご利用のご協力をお願いいたします。 |
| 医療DX推進体制整備加算について | 当院では、マイナ保険証の促進等、医療DXを通じた質の高い医療を提供出来るよう取り組んでおります。 ・オンライン請求を行っております。 ・診察室等にて、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を閲覧・活用し、診療を実施しております。 ・電子処方箋を発行する体制、電子カルテ共有サービスを活用できる体制を整備すべく検討を進めております。 |
| 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進について | 現在、ジェネリック医薬品を含む医薬品の供給が大変不安定になっております。 当院ではジェネリック医薬品の使用促進に努めておりますが、供給状況により、いつものお薬とは異なるお薬に変更する可能性があります。変更する場合は十分説明させていただきます。 |
| 一般名処方に関するお知らせ | 保険薬局において、銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者に安定的に医薬品を提供する観点から当院では、一般名処方を行っています。 薬剤の一般名称を記載した処方箋交付時、医薬品の供給状況や令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合又は患者の希望を踏まえ処方等した場合、選定療養費となることを踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分説明いたします。 |
| 施設基準にかかる手術の実績 | 【当院で2024年(1月~12月)に行われた施設基準のある手術】 (1) 区分1に分類される手術 ア. 頭蓋内腫瘤摘出術等 0件 イ. 黄斑下手術等 0件 ウ. 鼓室形成手術等 0件 エ. 肺悪性腫瘍手術等 0件 オ. 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 0件 (2) 区分2に分類される手術 ア. 靭帯断裂形成手術等 0件 イ. 水頭症手術等 0件 ウ. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0件 エ. 尿道形成手術等 0件 オ. 角膜移植術 0件 カ. 肝切除術等 1件 キ. 子宮附属器悪性腫瘍手術等 0件 (3) 区分3に分類される手術 ア. 上顎骨形成術等 0件 イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等 0件 ウ. パセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0件 エ. 母指化手術等 0件 オ. 内反足手術等 0件 カ. 食道切除再建術等 0件 キ. 同種死体腎移植術等 0件 (4) 区分4に分類される手術 49件 (5) その他の区分 ア. 人工関節置換術 215件 イ. 乳児外科施設基準対象手術(1歳未満) 0件 ウ. ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 0件 エ. 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用 しないものを含む)及び体外循環を要する手術 0件 オ. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及 び経皮的冠動脈ステント留置術 0件 |
| 保険外併用療養費特別の療養環境の提供に関する事項 | 入院にあたり、特別室の利用を希望される場合は、別途室料が必要となります。 「個室のご案内(PDF)」「特別室・個室料金表(PDF)」 |
| 保険外併用療養費医科点数表に規定する回数を超えて受けた診療に関する事項 | 運動器リハビリテーション料150日超えた患者で月13回以上のリハビリテーションを実施する方は特別料金1回 1,850円実費負担となります。 |
| 保険外併用療養費入院期間が180日を超える入院に関する事項 | 入院期間が180日を超える入院については、厚生労働大臣が定める状態にある患者を除きまして、別途料金が必要となります。 1日につき2,409円(通算対象入院料の基本点数15%相当) 詳細につきましては、医事課入院係までお問い合わせください。 |
| 療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収に関する事項 | 「文書料金一覧表(PDF)」「診療録開示費用(PDF)」 |
その他
当院では、日本循環器学会の行う循環器疾患実態調査による「レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究」に参加しています。
医師の負担軽減及び処遇の改善に資する体制
医師の勤務状況の把握等
- 勤務時間の具体的な把握方法
タイムカードにて管理
- 勤務時間以外についての勤務状況の把握内容
・年次有給休暇取得率
・育児休業、介護休業の取得率
- 特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系の策定
- 勤務体系の職員への周知
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組内容
- 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担
・初診時の予診の実施
・入院の説明の実施
・服薬指導
・静脈採血等の実施
・検査手順の説明の実施
- 連続当直を行わない勤務体制の実施
- 当直翌日の業務内容に対する配慮
- 短時間正規雇用医師の活用
医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制
- 看護業務の負担軽減
- 業務量の調整
- 看護助手との業務分担
- 主として事務的業務を行う看護補助者の設置
- 看護補助者の夜間配置
- 短時間正規雇用の看護職員の活用
- 多様な勤務形態の導入
- 妊娠・子育て・介護中の看護職員は、夜勤の減免、休日勤務の制限、他部署等への配置転換
- 夜勤従事者の増員